これから司法書士で独立を目指している人にとって、「公認会計士」と「税理士」の仕事は、かぶっている仕事とそうでないものがあり、その仕事の違いについて理解しにくい部分ありませんか?
ですので今回は、「公認会計士と税理士の仕事の違い」についてご説明しますので、ぜひ、チェックしてみてください。
この記事の目次
公認会計士と税理士の仕事の違いって何?
この記事では、よく業務が被っていると言われる「公認会計士と税理士の違い」について、仕事や収入面などの違いをご紹介していきます。
公認会計士とは簡単に
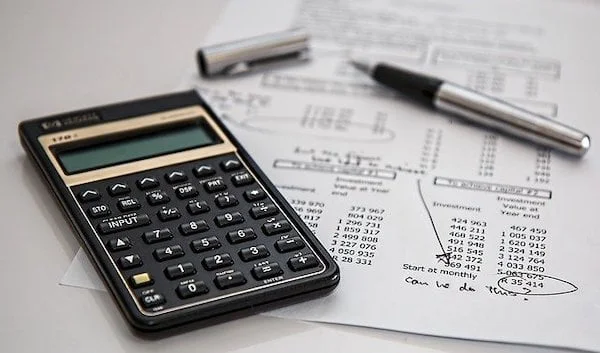
・公認会計士の仕事とは?
公認会計士とは一言でいえば、企業の会計が正しく行われているかチェックをする仕事です。
企業は、法律に則った経営が求められますが、複雑なお金の流れで意図しないきっかけによって、法律に抵触した会計処理を行ってしまっている場合も決して少なくありません。
こういったことが行われていないかチェックをするのが公認会計士です。
・会計処理が法律に準拠したものかをチェック
このチェック行為を監査といい、単に計算ミスがないかチェックするだけでなく、この会計処理が法律に準拠したものかも確認していきます。
そのため、単に帳簿の知識だけではなく、その背景による法律的な解釈も理解して会計におけるルール違反を探して指摘、さらには企業の会計担当者と共に会計の修正を行う仕事です。
この仕事から派生して、企業が法律に則った経営がされているかといったコンプライアンスのチェックや、さらに法律の知識を活かして有利な経営ができるようにするコンサルティング業務なども行っています。
また、企業に勤務して財務面の最高責任者(CFO)となる公認会計士もおり、内部から経営を支えるスタッフとして活躍しているケースも見られます。
・企業を支える公認会計士
このように、企業にまつわるお金の動き一切をチェック、指導し、さらには支えていくのが公認会計士といえるでしょう。
また、会社は公認会計士による会計監査が推奨されているので、会社経営をする上で公認会計士の存在はなくてはならないものなのです。
さらに大会社と認知される企業に関しては公認会計士による会計監査は義務なので、とくに重要な存在となります。
ちなみに大会社とは、貸借対照表の資本金が5億円以上、または、負債の部の合計額が200億円以上である株式会社を指します。地方でも数多く存在しているので、その分活躍の場の多い職業です。
税理士とは簡単に

・税理士の仕事とは?
税理士は一言でいえば個人や中小企業向きの税務を担当する仕事で、公認会計士に比べてより身近に会計のことを担当している仕事といえるでしょう。
例えば、農業をしている方や土地を売った方など、会社のお給料以外の収入がある方は確定申告をしなくてはいけません。
この確定申告を依頼して代わりに作成してもらったい助言を受けたりできるのが税理士です。
具体的には納税に必要な種類一式の作成や節税のためのアドバイスを行います。
本来、確定申告は本人が行うことが原則ですが、これを代行できる仕事として認められているのが税理士といえるでしょう。
・税務調査の代理人などの業務も
また、税務調査が入った場合は本人に代わって陳述や主張を行い、代理人として依頼者の立場を守ります。
さらに税務署の更正や決定に不服がある場合は、税理士が代理人として申し立てをすることもでき、税務署との間に入って対応してくれたり、税金の様々な相談ができるのも税理士です。
例えば、相続などで必要なアドバイスを受けられるのも税理士の仕事といえるでしょう。
ちなみにこの税理士の仕事は、公認会計士が行うこともできます。
税務会計事務所などと名乗っている場合は、公認会計士が税理士の仕事を兼務しているケースが少なくありません。
公認会計士と税理士「仕事の違い」

・クライアントの違い
公認会計士と税理士は仕事が混同してしまっているケースもありますが、大きな違いとして対象、監査、兼務できるかどうかといった点が挙げられます。
対象は、公認会計士が大企業を含めたすべての企業なのに対し、税理士は個人や中小企業です。
公認会計士は、大企業を含めたすべての企業が作成しなければいけない財務諸表を企業規模に関わらず作成します。
さらに大企業は子会社などの連結決算などを行う必要があり、より複雑さを増していることがほとんどで、そう言ったケースにも公認会計士は対応できます。
・会計監査の有無
しかし、税理士はあくまで中小企業で単独の決算を行う場合や商店、個人経営の飲食店、農林水産業といった第一次産業の方が対象です。
監査の有無も公認会計士と税理士の違いで、これが最も大きな違いといえるでしょう。
この監査は企業の会計が正確に行われているかチェックするもので、監査法人として複数の公認会計士が様々な視点から調べます。
そして監査を行ったという証明をすることで、企業の信用を証明したり、企業としての義務(前述のように大会社は監査が義務付けられています。)を果たせるのです。
・監査業務は公認会計士の業務独占
この監査業務は公認会計士の業務独占として行われているので、税理士はもちろんのこと弁護士もこれを行うことはできません。
この点が公認会計士と弁護士との大きな違いといえるでしょう。
・公認会計士は税理士業務も兼任可能
最後が兼務できるかどうかという点で、先ほども触れた通り公認会計士は税理士の業務も兼務できます。
つまり、実質的にあらゆる企業や個人の税に関するサポートが行えるのです。
一方、税理士は公認会計士の業務を兼務できません。
確かに公認会計士試験の一部試験科目の免除などが受けられますが、それ以上公認会計士の業務や資格が行使できないのです。
この差は大きく、公認会計士が税理士事務所も解説し、税務会計事務所を設置していることも珍しくありません。
公認会計士と税理士「年収の違い」

・公認会計士の方が高収入?
公認会計士と税理士の年収の違いもあります。
公認会計士は1,000万円を超える方が珍しくありませんが、税理士でそこまでの年収を稼ぐのは困難です。
この理由として、業務範囲の広さ、監査法人の報酬の高さが挙げられます。
公認会計士は税理士の業務も兼務できるので、その分収益を上げやすくなりますので、独立しても税理士が単独で業務を行うより多くの場面で収入が得られる仕組みです。
一方、税理士は税務のみなので監査の報酬が得られないため、公認会計士と税理士では収入が大きく異なるのです。
・勤務した場合の年収の差は?
また、勤務した際の公認会計士の年収が高いことも挙げられます。
公認会計士として勤務した場合、経理関係の幹部として勤務できる場合や外資系のビック4と呼ばれる監査法人に勤務できるチャンスがあります。
こういった場所やポジションに勤務できれば、公認会計士としてかなり高額な報酬がえられるのです。
一方で、税理士の場合は税理士事務所に勤務したり、一般企業の経理分野の勤務になるので、そこまで高額な報酬は期待できません。
しかし、いずれも高度な知識が求められる資格なので、公認会計士も税理士も高額な報酬を得られるのは事実です。
公認会計士と税理士「試験難易度の違い」

・試験難易度の違いは?
公認会計士と税理士の試験難易度は、共に高いものとなっていますが、その難易度は公認会計士に軍配が上がるでしょう。
まず、公認会計士は短答式と論文式の2つの試験があり、短答式試験を合格して初めて論文式の試験が受験できます。
一方、税理士試験は11科目から5科目を選択し合格する必要があります。
ただし、論文式試験などの2次試験はないので、その点は公認会計士試験よりも容易です。
・試験免除できることも
このような差があるだけでなく、税理士には試験自体が免除されるケースが存在します。
例えば公認会計士や弁護士の免許を持っていれば試験を受けることなく資格取得できます。
一方で公認会計士は弁護士資格を持っていたとしても科目の一部が免除されるだけであって、試験合格が与えられることはありません。
公認会計士と税理士「受験資格の違い」

・受験資格の違い
最後に公認会計士と税理士の受験資格の違いですが、結論をいえば共になく、学歴や性別、年齢に関わらず試験を受験することができます。
難易度に違いはありますが、大学卒業といった医療資格にみられるような受験資格はこれらの資格に存在しないのが事実です。
・共に難易度が高い国家資格
ただ、両資格とも高度な税務や会計、監査の知識が求められる資格なため、実質大学で専攻をしていないかぎり一発で合格するのは難しい資格として認知されています。
それでも、資格に興味があれば、大学在学中やリタイヤ後でもチャレンジできる資格なので、挑戦してみるのも良いかもしれません。
特に公認会計士は近年大学在学中に取得するケースも見られるようになっているので、決して可能性はゼロではないのです。





